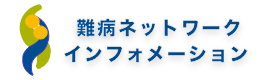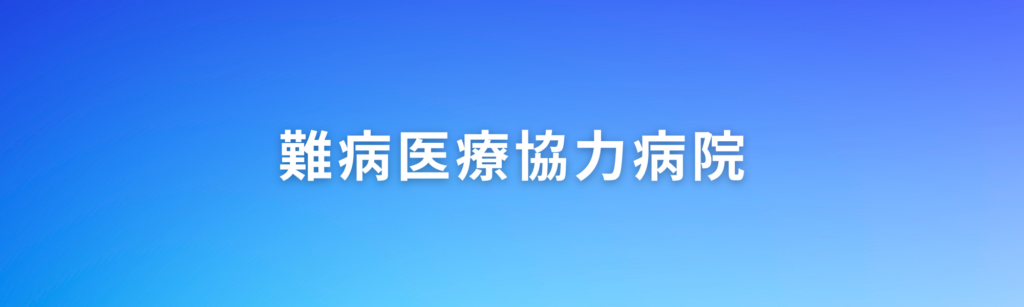慶應義塾大学と名古屋工業大学の共同研究グループは、神経細胞の働きを光で制御する「光遺伝学」の手法を活用した遺伝子治療薬の臨床試験(治験)を開始しました。この治験は、難病「網膜色素変性症」で失われた視覚の再生を目指すもので、光遺伝学の臨床応用としては国内初となります。
網膜色素変性症とは
網膜色素変性症は、目の内側を覆う網膜の視細胞が最初に障害を起こし、徐々に機能を失っていく進行性の失明難病です。通常4,000人から8,000人に1人の割合で発症し、世界の患者数は200万人以上と推定されています。現在までに根本的な治療法は確立されていません。
画期的な治療法の開発
慶應大学医学部眼科学教室の栗原俊英准教授らの研究グループは、名古屋工業大学の神取秀樹教授らが開発した「キメラロドプシン」という光感度の高い独自タンパク質を使用。光遺伝学の手法を応用することで、視覚再生効果と視細胞の保護効果があることをマウス実験で確認し、2023年10月に研究成果を発表していました。
この成果を基に、慶應大学発のスタートアップ企業「レストアビジョン」(東京都港区)がキメラロドプシンの遺伝子治療薬「RV-001」を開発。研究グループは既に視細胞の機能が失われた重症患者1人に対してRV-001を目に注射し、1例目の投与を完了しました。
治療のメカニズムと今後の展望
この治療法は、網膜にある双極細胞と呼ばれる神経細胞にキメラロドプシンを作る遺伝子を届け、視細胞の代わりに光の検知を担わせることを目的としています。現在のところ重い合併症は報告されていませんが、今後半年間の経過観察を通じて安全性と有効性を確認する予定です。研究グループは今後6~15人を対象に治験を継続する計画です。
栗原准教授らの研究グループは、「RV-001は視覚再生治療薬として世界初の実用化を目指す試みで、失明疾患に対する新たな治療法を提供する重要な一歩」と位置づけています。
光遺伝学の発展と応用
光遺伝学は2005年に米スタンフォード大学のカール・ダイセロス教授によって技術が確立されました。この技術は脳研究に大きく貢献し、ダイセロス教授は2020年に米国の医学賞であるラスカー賞(基礎分野)を受賞し、ノーベル賞の有力候補とされています。
2015年には理化学研究所・脳科学総合研究センターの利根川進センター長(当時)らが「光遺伝学によってマウスのうつ状態を改善した」と発表。現在では、うつ病や睡眠障害、依存症など精神疾患の研究や臓器の働きの制御を研究する分野で広く活用されています。
今回の治験開始は、光遺伝学の医療応用における重要なマイルストーンとなり、失明疾患に苦しむ患者に新たな希望をもたらす可能性があります。
参照元
光遺伝学を活用し、目の難病の視覚再生目指す 慶大など国内初の治験を開始 | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」