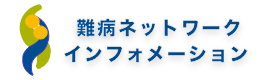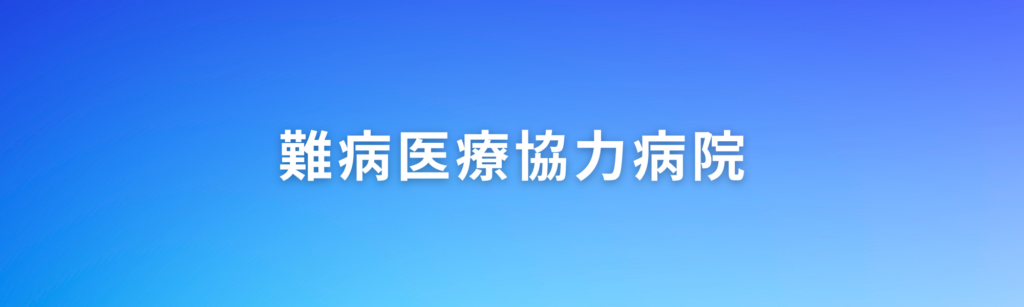東京慈恵会医科大学の研究チームが、シンガポールと米国の研究者と協力し、日本人に多い小児難病「シトリン欠損症」に対する新しい治療法を開発しました。この画期的な治療法は、核酸医薬(SSO)という特殊な薬を使って、遺伝子の異常を修復するものです。
シトリン欠損症とは
東京慈恵会医科大学の研究チームが、核酸医薬スプライシング制御オリゴヌクレオチド(SSO)を活用した、小児難病シトリン欠損症に対する新たな治療法の開発に世界で初めて成功しました。この画期的な研究成果は2025年2月18日、国際的に権威ある学術誌「Journal of Hepatology」に掲載されました。
研究の背景と成果
シトリン欠損症は日本人に高頻度で発症する遺伝性疾患で、SLC25A13遺伝子の変異が原因となる尿素サイクル異常症の一つです。現在までこの疾患に対する根治的治療は肝移植のみでしたが、今回開発された核酸医薬による治療法は、より低侵襲で有効性の高い新たな選択肢となることが期待されています。
革新的な遺伝子検査パネルの開発
研究チームは同時に、尿素サイクル異常症の8疾患(OTC欠損症、NAGS欠損症、CPS1欠損症、シトルリン血症1型、ASL欠損症、高アルギニン血症、HHH症候群、シトリン欠損症)の原因遺伝子に対し、深部イントロン変異を効率よく検出する遺伝子パネル「Prune」も開発しました。
このパネルにより、従来の検査方法では見逃されていた尿素サイクル異常症の原因遺伝子変異を発見できるようになり、より多くの患者さんに適切な診断と治療を提供できる可能性が広がりました。
国際共同研究による成果
この研究は、東京慈恵会医科大学小児科学講座の今川英里特任講師、大石公彦講座担当教授らの研究チームが中心となり、シンガポール科学技術研究庁(A*STAR)のJin Rong Ow博士、Keng Boon Wee博士ら、および米国マウントサイナイ医科大学のErnesto Guccione博士らのグループとの国際共同研究によって実現しました。
今後の展望
この研究成果は、遺伝性疾患に対する新たな根本治療の可能性を示すものであり、シトリン欠損症だけでなく、他の遺伝性疾患への応用も期待されています。核酸医薬を用いた治療法の開発は、小児難病に苦しむ患者さんとそのご家族に新たな希望をもたらす重要な一歩となりました。