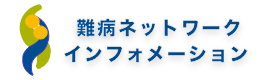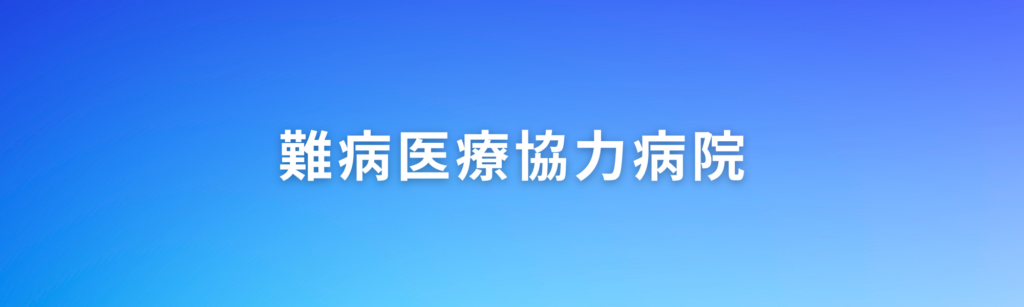新潟大学脳研究所の中島章博助教と河内泉准教授らの研究グループが、厚生労働省指定難病である「顕微鏡的多発血管炎(MPA)」「多発血管炎性肉芽腫症(GPA)」に伴う「脊椎肥厚性硬膜炎」の臨床的特徴・免疫病態・治療法・長期予後を世界で初めて明らかにしました。この研究成果は2025年3月19日、北米神経学会誌「Neurology」のオンライン版に掲載されました。
研究成果のポイント
病態の解明
脊髄を覆う硬膜に炎症が起こる脊椎肥厚性硬膜炎は、抗好中球細胞質抗体(ANCA)、特にミエロペルオキシダーゼ(MPO)に対する自己抗体(MPO-ANCA)を高い確率で持つことが判明しました。この疾患は、脳を覆う硬膜に炎症が起こる頭蓋肥厚性硬膜炎と比較して、ANCA関連血管炎の疾患活動性が高いことも明らかになりました。
特徴的な病理構造
研究チームは、肥厚した脊椎硬膜が特徴的な3層構造を形成することを発見しました。本来の硬膜の外と内に、肉芽腫性炎症巣と筋線維芽細胞を大量に含む2層が形成され、計3層構造となります。この肥厚硬膜の増大により脊髄が圧迫され、高い確率でミエロパチー(脊髄症)を引き起こします。
推奨される治療法
MPO-ANCAを持つ脊椎肥厚性硬膜炎には、以下の治療法が推奨されます
- 迅速な外科的減圧術(椎弓切除術と硬膜形成術)
- 寛解導入・維持のための免疫抑制療法(高用量の糖質コルチコイドと、シクロホスファミドまたはリツキシマブのいずれかを組み合わせた治療)
研究の意義
この研究は、これまで明らかにされていなかった脊椎肥厚性硬膜炎の病態メカニズムを解明し、適切な治療法を提示した点で非常に重要です。研究によって明らかになった病理学的所見は、硬膜とくも膜下腔が厳密に分離されていることや、骨髄と硬膜が微小血管を介して炎症細胞が移動できることを支持するものであり、硬膜が神経系へ果たす免疫機能・病態を理解する上で重要な示唆を与えています。
この成果は、ANCA関連血管炎による脊椎肥厚性硬膜炎の患者さんに対する診断・治療の向上に貢献することが期待されます。
研究チームと論文情報
この研究は、新潟大学を中核拠点とし、信州大学、帝京大学、北里大学、産業医科大学、新潟医療福祉大学、国立病院機構新潟病院などと共同で行われました。研究成果は「Neurology」誌に「Long-term clinical landscapes of spinal hypertrophic pachymeningitis with anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis」というタイトルで掲載されています。