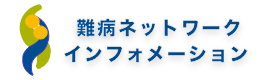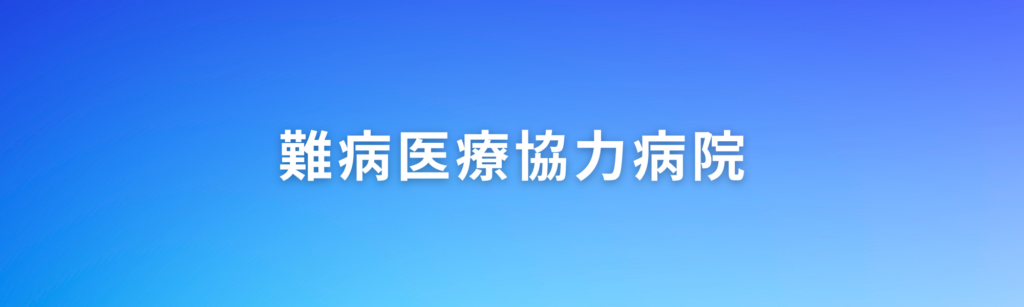日本医療政策機構(HGPI)難病・希少疾患プロジェクトは2025年3月28日、「難病・希少疾患 2025 ー難病法から10年、共に創る未来に向けてー」と題した論点整理(ディスカッション・ペーパー)を公表しました。このペーパーは、2014年に制定された「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」から10年を迎える節目に、今後の難病・希少疾患政策の方向性について構想したものです。
背景と目的
日本では指定難病の対象疾病数が現在341に上り、患者数は100万人を超えるとされています。難病・希少疾患の多くは発症機序が明らかでなく、明確な治療法が確立されていないため、患者や家族の心身の負担が大きくなりやすい特徴があります。
日本政府は1972年の難病対策要綱の制定以降、「研究開発の推進」「医療提供体制の整備」「患者支援(主に医療費助成)」を柱として難病・希少疾患対策を進めてきました。2014年には難病法が制定され、医療の推進だけでなく社会環境の整備も含めた方向性が打ち出されました。
このディスカッション・ペーパーは、2024年5月23日(難病の日)に開催されたシンポジウム「患者・市民の視点から考えるこれからの難病対策」での議論に加え、その後のデスクトップ・リサーチやヒアリング、関係者との議論を踏まえて作成されました。
5つの視点と論点
本ペーパーは、「社会環境」「医療」「家族・ケアラー支援」「社会参加」「イノベーション」の5つの視点から構成されており、それぞれの視点で以下の論点が提示されています。
視点1:共生を実現する社会環境の醸成
- 理解から具体的制度へ:患者・当事者の「生の声」を政策に反映させる必要性が強調されています。難病・希少疾患領域においても、社会の理解・共感から一歩進んで、合理的配慮に基づく具体的な制度に落とし込んでいく意識が求められている。
- 次世代に向けた啓発活動の必要性:若年層への働きかけを通じて、社会全体の関心・理解を深めることが重要です。教育現場での取り組みやSNSなどを活用した情報発信が期待されている。
- 多様な背景を持つ患者・当事者への理解:難病・希少疾患と共に生きる人々は、年齢、国籍、居住地域など多様な背景を持っており、そうした多様性にも目を向ける必要がある。
視点2:患者・当事者の不安を解消できる医療システムの実現
- 「診断ラグ」の短縮:薬局・地域・学校・職場といった多様なアクセスポイントを拡充し、早期発見・早期対応につなげることが重要。
- 早期診断・治療の実現:技術革新と医療機関連携の促進により、診断から専門医へのスムーズな接続を実現することが期待されている。
- ライフコースアプローチに基づく制度設計:個別性や長期療養に対応できる柔軟な制度が必要とされています。特に小児期から成人期への移行期医療の課題解決が求められている。
視点3:家族・ケアラーの尊厳が守られる施策の整備
- 家族・ケアラーの支援:家族・ケアラーの置かれている実態を明らかにし、負担軽減と社会参加・自己実現を支援する必要性が指摘されている。
視点4:社会参加(教育・就労)機会の確保と充実
- 多様な学びの環境の保証:難病・希少疾患と共に生きる子どもが、状況に応じて学校の種別や体制を選択できる柔軟なシステムの構築が求められている。
- 就労環境の多様な選択肢の整備:経済的自立を支えるため、既存の障害者雇用の枠組みを活用しつつ、難病・希少疾患を対象とした独自の就労支援制度の拡充が期待されている。
- キャリア構築を実現できる就労環境:治療と仕事の両立を図りながら中長期的なキャリアを構築できるよう、本人を中心に主治医・職場が細やかに連携・調整することが重要。
視点5:患者・当事者がイノベーションを享受できる政策環境の実現
- 公的医療保険制度の堅持と負担のあり方の見直し:難病・希少疾患こそ公的医療保険制度の枠組みの中で支えられるべきであり、制度の持続可能性を高めるための思い切った改革が必要とされている。
- 新たな診断・治療技術の実現と実装:患者データの収集体制の構築や、官民一体となった開発への政策的支援が不可欠である。
- 患者・当事者の参画:「患者の声を届ける」段階から「共に創る(共創:Co-creation)」へ進んでいくことが期待されている。
今後の展望
このディスカッション・ペーパーは、難病法制定から10年という節目に、患者・市民の視点から難病・希少疾患政策の今後の方向性を示したものです。2025年度からは指定難病の認定基準がアップデートされるなど、医学の進歩とともに制度も変化を続けています。
また、2025年5月には大阪・関西万博のテーマウィークスで「希少疾患」をテーマにしたプログラムが予定されており、難病・希少疾患に対する社会的関心を高める機会となることが期待されています。
難病・希少疾患と共に生きる人々が、必要な医療を受けながら社会参加できる環境を整えるためには、患者・当事者を中心に、医療者、研究者、行政、企業など多様なステークホルダーが連携し、共に未来を創っていくことが重要です。