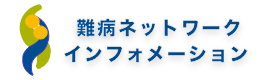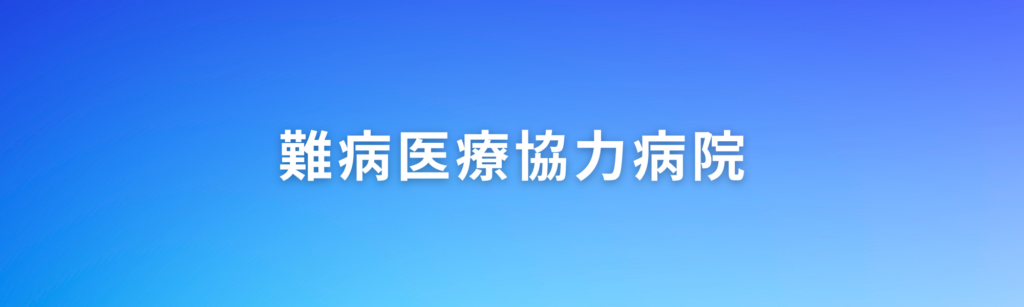近年、難病患者の雇用促進が注目を集めています。特に山梨県では、全国初となる「障害者手帳の有無を問わない難病患者枠」を設け、県正規職員として採用する制度を導入しました。この取り組みは、難病患者にとって新たな就労の道を開く画期的な一歩となっています。
背景:難病患者の就労課題
日本には約700万人の難病患者がいるとされ、その多くが働く意欲を持ちながらも、法的支援や社会的認知の不足により就労機会を得られない状況にあります。特に障害者手帳を持たない難病患者は、法定雇用率の対象外であるため、企業や自治体からの積極的な雇用が進みにくい現状があります。
山梨県の新制度
山梨県では、難病患者が抱える課題に対応するため、「障害者手帳の有無」に関わらず採用可能な枠を設けました。この制度は、地方議員や支援団体との連携による長年の取り組みが実を結んだものです。これにより、体調に応じた柔軟な働き方や在宅勤務など、多様な就労形態が可能となり、多くの難病患者が社会参加への希望を抱けるようになりました。
全国への波及効果
この取り組みは他の自治体や企業にも広がりつつあります。例えば、短時間勤務やリモートワークといった柔軟な雇用形態が注目されており、難病患者だけでなく介護や子育て中の人々にも働きやすい環境を提供するモデルケースとなっています。また、この動きは労働力不足解消にも寄与すると期待されています。
今後の展望
現在、支援団体は「難病者の社会参加白書」の発行や啓発活動を通じて、さらなる認知拡大と制度整備を目指しています。また、国レベルでも法定雇用率への算定対象拡大を求める動きが進行中です。これらの取り組みは、多様な背景を持つ人々が安心して働ける社会づくりへと繋がるでしょう。
山梨県から始まったこの取り組みは、難病患者だけでなく、多様性を尊重する社会全体にとって重要な一歩となっています。
ソースURL: https://www3.nhk.or.jp/lnews/kofu/20250401/1040026210.html